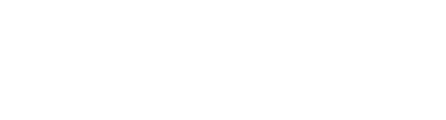3Dデータのビジネス活用が大きく変わろうとしている。建設業や製造業、エンタテイメントなど一部の業界では活用が進んできたが、今後はあらゆる業界で3Dデータが活用されるかもしれない。
「Xデーはすぐそこ。ビジネスでも日常でも、すべてのビジュアル素材が3Dデータ化される日は近い。流れに乗り遅れずビジネスチャンスをつかんで欲しい」と熱く語るのが、東京大学発のAIスタートアップ、bestat代表の松田尚子氏だ。
AI研究の権威「東京大学松尾研究室」出身の松田氏は、独自開発したアルゴリズムにより、あらゆるものを3Dデータ化できる環境を提供。業界に旋風を巻き起こしている。今回、MetaStep(メタステップ)編集部は松田氏に独占取材。AIにより3Dデータの活用がどう変わるのか、ビジネス活用にいかに応用できるのか、その全貌に迫った。(文=MetaStep編集部)

経済産業省、海外留学からAIの道へ
―スタートアップの代表としては異色の経歴をお持ちだと伺ったのですが。
確かにそうかもしれませんね(笑)。
キャリアのスタートとしては経済産業省に入省し、その後、米コロンビア大学に留学しました。その時は、データサイエンスなど、今のAIにつながる領域について学ぶ機会に恵まれました。
日本に戻ってからは、海外で学んだことを政策に役立てることができればと思っていたのですが、政策はデータだけでは決めることができないんですよね。いわゆる政治的な要素もかなり絡んできます。
一方、帰国後は松尾先生のもとで研究者としての活動も行い、実際に企業の方にアルゴリズムを使っていただくといった経験も積んでいました。政策提言に関わったり、純粋に研究者という立場で活動を続けたりするよりも、ビジネスとしてAIなどのテクノロジー領域に関わったほうがより自身の知見を活かせるんじゃないかなと感じるようになったんです。
そこで2018年にbestatを設立し、AIによる3Dモデリングの技術開発に本格的に着手し始めました。bestatでは、「3D.ai」というサービスを開発・提供しています。スマートフォンなどで撮影した写真をもとに、AIが自動で3Dデータを作成してくれます。
これまで、3Dデータを人の手で作成していた時は、1つのモデルを作るのに10~20時間程度かかることもありました。「3D.ai」を導入することで作成時間の7〜8割を削減できた事例もあります。現在はまだ、製造業、建設業など、元々3Dモデリングの技術を導入していた業界での導入が主ですが、今後はデジタルツインやメタバースなど、より多様なジャンルで活用が進むのではと思っています。
3Dデータ活用は着実に広がっている
.jpg)
―3Dデータを用いることのメリットについてお伺いします。
「2Dよりも3Dの方が人は直感的に理解できる」というのが一番のメリットです。
人間が2Dのものを見た時は「情報処理」の脳が働きます。一方、3Dのものを見た時は「感情処理」の脳が働くことがわかっています。人は3Dの情報をより「エモーショナル」なものとして捉えようとするんです。
感情が揺さぶられることになるので、2Dよりも3Dのものに対して直感的に「楽しさ」や「嬉しさ」を感じやすい。人の脳はそういった作りになっています。
その結果、より創造力が働くことになるので、ビジネスにおいても個人においてもクリエイティブな行為がどんどん楽しくできるようになります。これが、3Dがもたらす一番のメリットなのかなと考えています。
―3Dを用いることで人の行動が変わった具体例などはありますか?
.jpg)
ECサイトでの例ですが、サイト内に3Dデータを掲載した場合、3分の1程度の人は必ずそのデータを触るんですよね。実際に3Dのモデルにタッチして、グリグリとスマホやパソコン上でいじるイメージです(笑)
また、ある調査では3Dを用いた広告は、2D広告に比べて700%以上も見てもらえたと言う調査結果もありました。
先ほどの「直感的」という話にもつながりますが、2Dと3Dのものが並んでいれば、3Dのほうを触りたくなるのが人間の性なんですよね。
―たしかに、Amazonなどでも3D表示の商品モデルがあると、つい触ってしまいますね。
AmazonなどのECサイトも、あるいはSNSもですが、3Dデータを利用できる場は急速に増えています。今の時代、ホームページにせよSNSにせよ、「写真」を載せない会社ってありませんよね?
どんな会社のホームページも、あるいは個人のSNSも、人はみな必ず写真を撮り、それをメディアに載せることで情報を伝えています。さらに動画の利用も増え続けています。
これからは、さらに3Dデータの利用が次の情報伝達手段として、当たり前になっていくと考えています。
写真を使わない会社や個人がいないのと同じように、3Dデータを作らない会社や個人はいなくなる。まさに3Dデータは人間にとって「当たり前」の技術になると思っています。
3Dデータのビジネス活用可能性
.jpg)
―MetaStepの読者の中には、メタバースやデジタルツインに興味がある人も多数います。そのような領域において、AIを活用した精緻な3Dモデルはどのような利用価値があるのでしょうか?
実在するものを3Dモデル化し、NFTとして扱うといったユースケースはこれから増えると思います。そのような場合においても、3Dモデルはできるだけ「真実の状態」に近い方が良いと考えています。
例えば、「茶色のバッグ」というだけなら、多少粗っぽい3Dモデルでも許されます。ところが、「ルイ・ヴィトンの高級なバッグを3Dモデル化する」という話になれば、低品質の3D技術では許されないですよね? 誰が許さないかというと、ルイ・ヴィトン側が許さないはずです。
有名ブランドが自社製品を3Dモデル化する場合、「大まかな形状はイケてるように見えるけど、実は細部はいい加減」という3D技術では、絶対に世に出すことはできません。自分たちのブランドの価値を毀損することになりますから。
事実として、「3D化する技術の方が低品質なのではないか?」ということを理由に、3Dモデルの領域にはまだ手を出さないという有名企業は多いです。
裏を返すと、精緻な3Dモデルをより手軽に作成できるようになれば、メタバースやデジタルツインの領域に参入する企業は一気に増えると思います。私たちの「3D.ai」の技術も、ぜひ業界に風穴を開けることに貢献できればと考えています。
今は何合目?驚きのスピードで進む技術革新
.jpg)
―一方で、3DにせよAIにせよ、難しそうだなという印象を持つ読者は多いと思います。実際のところ、「ビジネスパーソンが手軽に使える」というところをゴールとするなら、今の3Dモデル技術は何合目まで来ているのでしょうか?
何合目という表現はなかなか難しいですね(笑)
AIで3Dモデルを作るのにかかる計算時間は、例えば昨年から今年にかけてと言う短い期間でもなんとおおよそ5分の1程度になっています。やはりAI領域での技術革新の度合いが相当大きかったので、かかる時間は一気に減りましたね。
ChatGPTなども同じですが、良くなる時は本当に一気に前進します。
プレプリント(査読を通過する前の論文)含め、様々な論文を日々チェックしていますが、本当に毎日のように技術革新が起きています。また来年、新しい技術が出てくれば、かかる時間はさらに今の5分の1になるかもしれません。そうなると、わずか2年で25分の1になることさえありえます。そうなってくると時間や金銭的コストが大幅に下がり、今とは全く違う使われ方をしてくるはずです。
先ほどの質問への回答に戻りますが、「山の何合目まで来ている」どころか、一瞬で「山を見下ろす位置まで来ていた」とか「いつの間にか山ですらなくなっていた」ということもありえると思います。ホント何が起こるかわかるくらい、いろんなこと起きているので、毎日が驚きの連続です。
―「AI」の発展は著しい印象があります。今後、AI技術の成長によって3Dの分野ではどんなことが実現しそうですか?
3D分野における生成AIは相当大きな可能性を秘めています。
例えば、ゲームで使う3Dモデルを生成するにしても、ゲームの雰囲気にあうコンテンツを作ることってとても大事ですよね。
3Dモデルとしては精緻で完成度が高かったとしても、世界観が合わなかったり、風合いが違ったりするコンテンツは共存できません。どのゲームにもメタバースにも、それぞれ世界観があるので、そこにマッチするデータを作れるようなAIを開発することは重要です。
わかりやすく言うと、ポケモンの世界観の中にファイナルファンタジーの風合いを持ったモデルを紛れ込ませることはできないですよね?明らかに浮いて見えちゃうじゃないですか。そういった雰囲気を合わせるのも生成AIの得意分野と言えます。
―たしかに、世界観が変われば3Dモデルに求められるものも変わってきますね。今後、どのように3D技術は進化していくとお考えでしょうか?
現在でも製造業や建設業ではよく3Dモデルが使われています。「この機械のあそこの部品はどうなっているのかな?」という確認や共有のために使われています。いわゆるデジタルツイン、事実の確認みたいな使われ方です。
今後を考えると、「静的」な物から「動的」な物へと変化していくと思います。「動いているもの」、つまりは生き物などをデジタルツインで見られるようになってくるはずです。
歴史から見ても、静的なものから始まり、動的なもの追い求める傾向にあります。人ってどうしたって感情のいきものですから、感動することや楽しいことを追い求めるんですよね。その点で考えても、デジタルツインの文脈も、事実の確認とか事実の共有などから、その『場』を共有する、『時間』、『空間』を共有する、と言うような流れになってくると考えています。そうすることで、『感動』までも共有できるようになるということです。
人は『場所・時間・空間』を共有した状態で何かを体験することで感情が大きくなることがありますよね。例えばスポーツの試合も、自分の目の前で、すべて(場所・時間・空間)を共有した状態で見るからこそ感動するわけです。
3D技術が発達することによって、動きのあるものがリアルタイムに、デジタルツイン上で表現できるようになってくる。今までは伝えることができなかったものが伝えることができる。その場にいなくても「感動の共有」ができるようになっていくと思います。エンターテインメントの新しい形ですよね。動的な物を3Dで表現できるようにすることが私自身、3D技術を扱う上で最も楽しみなところでもあります。
この新しい形のデジタルツインは、ビジネスにも非常にインパクトを与えるのではないかと思います。
AI時代に「人にしかできないこと」とは
.jpg)
―感動の共有までできるようになるとは、正直驚きです。AI、3Dのいずれもが急速に進化を続ける中、人間に求められる役割はどのようなものになっていくのでしょうか?
どんなにAIが発達しても、AIは「何が美しいか」「何が面白いか」ということは決められません。
そういう判断こそ、その人らしさ、つまり個性がすごく出るものです。その人の人生観、価値観、バックグラウンドなどが全部出ますが、そこには何が上とか下など、あまり関係ないですよね。正しさに優劣は付けられない。AIは「これと似たようなものを作りなさい」と言われたら作るのは得意ですが、何が良くて、何が美しくて、何が素晴らしいのか、それは人でなければ決めることはできません。
順番をつけるわけでなく、人それぞれの価値観やバックグラウンド、歩んできた人生、そういったものに基づいて、その人らしさが表現できる世界を作ることに、人が時間を使える時代になればといいなと思っています。
自分は何が好きなのか。それをより自由に表現できるようになるツールも増え、そしてメタバースのような空間でお互いの好きをシェアできるような場も増える。そうした、その人らしさが表現できる世界ができてくると思います。やっぱり人って「楽しさ」が一番の原動力なんだと思います。
ビジネス領域でも今では考えられないような活用が進んでいるはずです。先ほども話しましたが、技術の進化は一瞬です。ついていくのが大変なくらい、とにかくその流れの真ん中にいたら、さすがにわかることはあるだろうと思っています。
―近い将来、AIを使い、誰もが手軽に3Dで表現する未来が想像できました。最後に読者へのメッセージをお願いできますか?
いきなり3DデータやAIが自社ビジネスでどのように活用できるか、と考えるのは難しいと思うので、まずは気軽に、自分が今身近で好きなもの、関わっているもので、それが3Dになったらどうなるのかな?と考えてみてはいかがでしょうか?AIも3Dも使うのは我々「人」ですからね、楽しみながら探してみて欲しいです。きっと面白い物もあると思うので、ぜひ私にも教えて欲しいです。


.jpg)